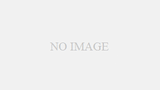Webサイト、ポスター、雑誌のページを眺めているとき、その整然としたレイアウトに、静かな説得力と心地よさを感じたことはありませんか?
多くの場合、その背後には「スイス・スタイル」として知られるデザインの考え方が息づいています。
それは単なる見た目の流行ではありません。
情報を明瞭かつ客観的に伝えるための、時代を超えた普遍的なアプローチです。
今回は、このスイス・スタイルの特徴と、その核となる「グリッドシステム」の本質を、紐解いていきましょう。
美しさの前に まず 伝えること
スイス・スタイル(別名:インターナショナル・タイポグラフィック・スタイル)が誕生したのは、1950年代のスイス。
当時の社会が求めたのは、多様な言語や文化を持つ人々の間で、誤解なく情報を伝達する手段でした。
この様式の根底にあるのは「客観性」です。
デザイナー個人の感情や芸術的な表現を前面に出すのではなく、伝えるべき情報そのものを主役に据えます。
あたかも、熟練のコンシェルジュが自己主張せず、ゲストが必要とする情報だけを的確に差し出すように。
その本質は、3つのキーワードで解き明かすことができます。
明瞭性
誰が見ても、いつでも、同じように理解できること。
余計な装飾を削ぎ落とし、伝えたいメッセージの純度を高めます。
機能性
「Form follows function(形態は機能に従う)」という言葉に象徴されるように、デザインのすべての要素には明確な役割があります。
美しさは、機能性を追求した結果として、副次的に生まれるものなのです。
秩序
情報が無秩序に配置されていては、脳はそれを理解するために余計なエネルギーを消費します。
情報を整理し、秩序を与えることで、受け手はストレスなく内容に集中できます。
この「秩序」をデザインの世界で実現するための最強のツールが、グリッドシステムです。
グリッドシステム 見えない情報の骨格
グリッドシステムとは、ページ上に引かれた「見えない格子状のガイドライン」のことです。
文章、見出し、写真といった要素を、この格子に合わせて配置していきます。
初心者の方は「なんだか不自由そう」と感じるかもしれません。
しかし、これは単なる制約ではありません。
むしろ、創造性を解き放つための土台となるのです。
例えるなら、建築における設計図、あるいは音楽における楽譜のようなものだと想像してみてください。
設計図としてのグリッド
柱や梁の位置が決められているからこそ、建築家は安全で機能的な空間を創造できます。
グリッドはデザインにおける構造の安定性を保証し、デザイナーがコンテンツの配置に悩む時間を減らし、より本質的なクリエイティブに集中させてくれます。
楽譜としてのグリッド
音符が五線譜の上に配置されることで、美しいメロディが生まれるように、デザイン要素がグリッドに沿って配置されることで、視覚的なリズムとハーモニーが生まれます。
ページをめくっても、Webサイトをスクロールしても、一貫した心地よいリズムが感じられるのは、このグリッドのおかげです。
グリッドシステムがもたらす恩恵は計り知れません。
一貫性の創出
すべてのページで同じグリッドを用いることで、デザイン全体に統一感が生まれます。
これは、ブランドの信頼感を醸成する上で極めて重要です。
効率性の向上
デザインの意思決定が迅速かつ論理的になります。
「なんとなく、ここに置く」という曖昧な判断がなくなり、チームでの共同作業もスムーズに進みます。
柔軟性の確保
一見矛盾しているようですが、強固な構造は、実は柔軟性を生み出します。
例えば、Webデザインにおけるレスポンシブ対応。
画面サイズが変わっても、グリッドのルールに基づいて要素を再配置すれば、デザインの秩序を保ったまま最適なレイアウトを自動的に生成できるのです。
タイポグラフィが主役になる理由
スイス・スタイルにおいて、タイポグラフィ(文字のデザイン)は単なる装飾ではなく、情報を伝えるための最も重要な機能要素です。
特に、Helveticaに代表される「サンセリフ書体(文字の端にセリフと呼ばれる飾りがない書体)」が好んで使われました。
その理由は、クセがなくニュートラルで、可読性に優れているからです。
文字の大きさ、太さ、行間、配置のすべてが、グリッド上で緻密に計算されます。
見出しは大きく、本文は読みやすく、注釈は控えめに。
この視覚的な階層(ヒエラルキー)によって、読者は情報の優先順位を瞬時に理解し、最も重要な情報から自然と読み進めることができるのです。
現代におけるスイス・スタイルの価値
スイス・スタイルは、半世紀以上前に生まれたにもかかわらず、情報が爆発的に増加した現代において、その価値を一層高めています。
私たちが日常的に触れる優れたUIやWebデザインの多くは、この考え方を色濃く受け継いでいます。
ユーザーが直感的に操作できるアプリケーションのレイアウトも、異なるデバイスで同じように情報を得られるWebサイトも、その根底には「客観性」「明瞭性」「機能性」を追求するスイス・スタイルの精神が流れています。
まとめ
スイス・スタイルとグリッドシステムは、単なる過去のデザイン様式ではありません。
それは、情報が氾濫する世界の中で、伝えたいことを、伝えるべき相手に、最も誠実に届けるための普遍的な考え方です。
一見すると地味で、制約が多いように感じるかもしれません。
しかし、その静けさの奥には、どんな流行にも揺るがない、論理的で力強い美しさが宿っています。
もしあなたが、ご自身のデザインに「説得力」や「一貫性」を持たせたいと考えるなら、まずはページの中に「見えない情報の骨格」を意識することから始めてみてはいかがでしょうか。
その一本の線が、あなたのクリエイティブを、より高く、より遠くへと導く道標になるはずです。
投稿者(アートディレクター・デザイナー 山本真一郎)は、SIROPCOLORという屋号にて、ブランド戦略策定やブランディングに取り組むクライアントをサポート。グラフィック、Web、UI/UXなどデザインの領域を横断して、企業・製品・サービスの本質を捉えたコミュニケーションデザインに取り組んでいます。