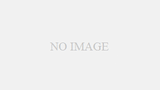私たちは普段、「目で見ている」と信じています。
しかし実際には、私たちが感じている「見え方」は、網膜に届いた光の情報を脳が解釈して再構築した像です。
その解釈の過程で生じるズレや予測の誤差によって、現実とは異なる知覚が生まれることがあります。
この現象こそが「錯視」です。
錯視はなぜ起こるのか?
錯視は単なる目の錯覚ではなく、脳の情報処理の効率化の副産物です。
私たちの脳は、膨大な視覚情報を瞬時に処理するために、細部を正確に分析するのではなく、過去の経験やパターン認識を使って推測します。
多くの場合、この推測は的確ですが、特定の条件下では現実とのズレが発生します。
たとえば、同じ面積の正方形と円がある時、正方形の方が、やや大きく感じられるのは、形の外周や縦横比に対する感度の違いによるものです。
私たちの脳は、幾何学的な正確さよりも、「これまで多く見てきた形の平均的な印象」を優先して解釈します。
デザインと錯視の深い関係
デザインは「見せ方」を操る仕事です。
錯視は、避けるべき誤差ではなく、意図的に利用できる視覚効果として機能します。
サイズ補正
ロゴやアイコンなど、異なる形状を同一レベルとして隣り合わせに並べる場合、見え方の差を補正するために、形状の特性に合わせてそれぞれ拡大・縮小させます。
奥行き感の演出
ドロップシャドウやグラデーションを施すだけで、平面に立体感が生まれます。人間の脳は、光源や陰影から空間の奥行きを無意識に推測するためです。
視線誘導
矢印や人物の視線、斜めの線などを使って、閲覧者の目線を自然に動かすことができます。これも錯視の一種で、心理的な流れをつくるテクニックです。
強調と抑制
背景色や周囲のパターンを変えることで、同じ色でもより鮮やかに、あるいは落ち着いて見せることが可能です。UIデザインや広告では重要な手法です。
錯視は「欠陥」ではない
錯視は、人間の視覚システムの不完全さを示すものではありません。
むしろ、限られた情報から素早く状況を理解するための、高度な生存戦略です。
森や街中で瞬時に距離感や形を把握できるのも、この推測機能のおかげです。
錯視は、その機能が特定の条件下でズレを生じた結果にすぎません。
この視点を持つと、「錯視をどう避けるか」ではなく、「錯視をどう活かすか」という発想に変わります。
ポスター、パッケージ、Webサイト、どの分野でも、錯視を上手く組み込めば、印象的で記憶に残るビジュアルを作ることができます。
実際の活用例
ロゴの微調整
ロゴは、幾何学的な正確さだけではなく、見た目が整うように錯視補正も施されています。
道路標識
遠くからでも読みやすいよう、文字や矢印に錯視を利用したサイズや太さの調整が行われています。
UI
ボタンの高さや角丸、影のつけ方などによって、押しやすく感じるような錯視効果が仕込まれています。
まとめ
錯視は、脳がつくり出すもうひとつの現実です。
デザイナーにとってそれは、避けられない制約であり、同時に魅力的な武器でもあります。
形や色を扱うとき、「事実」と「実際」を一致させるのか、それとも意図的にずらすのか、この選択ひとつで、作品の印象は大きく変わります。
次に何かをデザインするとき、ぜひ「人の目がどのように世界を解釈しているか」に意識を向けてみてください。
そこには、数値では測れない「視覚のデザイン」の奥深い世界が広がっています。
投稿者(アートディレクター・デザイナー 山本真一郎)は、SIROPCOLORという屋号にて、ブランド戦略策定やブランディングに取り組むクライアントをサポート。グラフィック、Web、UI/UXなどデザインの領域を横断して、企業・製品・サービスの本質を捉えたコミュニケーションデザインに取り組んでいます。